2019年末に中国武漢に出現し、世界中に伝播した新型コロナウイルス感染症。私たちは今までに経験したことがないウイルス感染症と共に生きていくことを強いられてしまいました。そこで、現時点でわかってきたこのウイルスについて簡単にまとめてみました。
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)はコロナウイルス科に属するRNAウイルスです。コロナウイルスはヒト以外にもコウモリ、ブタ、ネコ、ネズミ、モグラ、ラクダ、トリなどの動物に病原性を示すものがたくさん存在します。これら多くのコロナウイルスは、オルソコロナウイルス亜科とレトウイルス亜科に分けられ、オルソウイルス亜科はアルファコロナウイルス属・ベータコロナウイルス属・ガンマコロナウイルス属・デルタコロナウイルス属に分類されます。そのうち以前より知られているコロナウイルスは4種類あり、ヒトの風邪ウイルスで軽症の上気道感染症の原因ウイルスでした。これらに加え、2002年にSARS(重症急性呼吸器症候群)コロナウイルスと2012年にMERS(中東呼吸器症候群)コロナウイルスがヒトに重篤な呼吸器感染症を起こすウイルスとして発見されました。そして今回、ヒトに病原性を示すコロナウイルスとして新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)が発見されました。このSARS-CoV-2はベータコロナウイルス属で、ヒトのウイルスではSARSウイルスに近い関係にありますが、野生のコウモリから分離されたコロナウイルスとは更に近い関係にあり、このコウモリのウイルスから派生したウイルスが何らかの理由でヒトに感染して流行がはじまったと考えられています。
コロナウイルスは一本鎖のRNAを遺伝子とするウイルスで、ウイルス粒子はエンペローブ(脂質二重膜)に包まれています。ウイルス粒子の表面はエンペローブから突き出したスパイクと呼ばれるSタンパク質の突起物があります。コロナウイルスのスパイクは大きく王冠(crown)のように見えることが名前の由来になっています。スパイクはウイルスが感染するときに細胞上のレセプターに結合する機能を持っています。以前流行したSARSコロナウイルスはアンジオテンシン変換酵素2(ACE2)をレセプターとして利用していますが、SARS-CoV-2もACE2を利用していることが実証されました。このレセプターは下気道(肺胞上皮)、上気道、口腔粘膜、舌、小腸、心臓、腎臓にも発現しています。
過去の重篤な病原性を持つコロナウイルス(SARS、MERS)の流行はパンデミックに至りませんでした。なぜ今回の新型コロナウイルス感染症がパンデミックを起こしたのか、それは、体内における増殖特性の差にあると考えられます。SARS・MERSウイルスは下気道(肺)で増殖していました。このためウイルスがなかなか体の外に出にくい状態でした。今回のSARS-CoV-2は下気道のみならず上気道でも増殖し、重篤化の前からたくさんのウイルス粒子が上気道分泌液に排出されていたことで、容易にウイルスが体の外に排出されてしまい、従来の感染重症者隔離策では対抗できなかったのです。(SRASはこの隔離策で収束しています。MRASはラクダがウイルスをもってしまったため完全には収束に至っていません。)
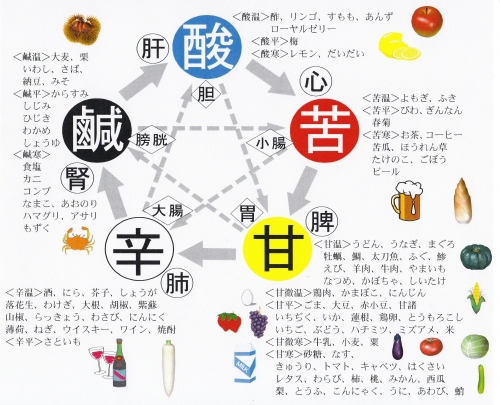 日野にある横浜成寿山善光寺さんの「やすらぎ通信」のコラムを担当したので、内容をご案内いたします。
日野にある横浜成寿山善光寺さんの「やすらぎ通信」のコラムを担当したので、内容をご案内いたします。